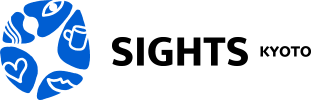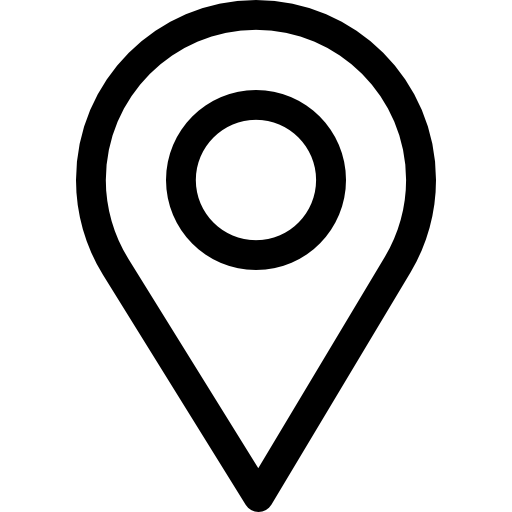2030年に開業を目指す「SIGHTS HOTEL」。実は水面下で、秘密裏にプロジェクトは進められているとか、いないとか……?この連載では、「SIGHTS HOTEL」が完成するまでに至った苦悩や試行錯誤の様子や姿を、ありのままに映していきます。ぜひ、読者の方も一緒に「SIGHTS HOTEL」を考え、妄想してもらうきっかけ作りになれば良いなと思っています!
具体的には、主に「SIGHTS HOTEL」についてゼロから考える「クレイジーキルト」で議論された内容を踏まえ、西澤夫妻が得た気づきや学びをまとめていきます。連載企画のインタビュアーを務めるのは俵谷龍佑(たわらや・りゅうすけ)です。西澤夫妻とは1988年生まれ、同世代!
・・・
Vol.2は、「人間らしさ」や「本質」といった哲学チックな話に。さらには、そこから発展して「ソサエティ」や「プリンシプル」など聞き慣れない用語も登場!?果たして、どのような内容になっているのか。ぜひ、じっくり読んでみてください。
Contents
民宿とゲストハウスから考える「人間らしさ」
前回は、「ゲストハウス」や「民宿」起点でSIGHTS HOTELを考えることが議題にあがったそうですね。どんなお話になったのか教えてください。
奈月さん:ゲストハウスには何度か泊まったことがあるので、今回は子どもの頃に行ったような民宿に家族で泊まることにしました。
確かに民宿はアットホームでしたが、ゲストハウスのような旅人同士の交流はないし食事も残してしまうほど量が多かったんです。また、部屋は清潔でしたがトイレのスリッパが「おぱんちゅうさぎ」で(笑)。今の時代に合わせたサービスやデザインにアップデートされていない印象を受けました。
徹生さん:自分らが目指すものとは違うだけで、もちろんそれを否定するわけではないです。僕らが考える人間らしさには、ウェルカムな空気感だけでなく、向上心や挑戦、泥臭さなどが含まれているのかなと思いました。
「人間らしさ」には、向上心や挑戦といった意味合いも含むんですね。
奈月さん:民宿に行った次の日に「うめきた・グラングリーン大阪」に立ち寄ったんですね。敷地内には、遊具メーカー・ボーネルンドが運営する「プレイキューブ」と、ヒルトングループのライフスタイルホテル「キャノピー」があって、そこを訪れました。
子供がプレイキューブで遊んでいるときに、スタッフの方から「お母さんやお父さんを集めて座談会を開催したいので、夕方ごろに集まってもらえませんか」と声をかけられたんですね。
徹生さん:ボーネルンドは遊具をとおした知育や教育を行っていて、プレイキューブに関しては、もう一歩進んで「子供だけではなく大人も学べる」みたいなコンセプトがあるんですよ。
奈月さん:プレイキューブは、今プレオープン中で来年春の本格オープンに向け、「どういうコンテンツを作っていけば良いか、みんなと考えていきたい」と言っていました。完全にハードを作り切らずに利用者の声を聞きながらソフトを作っていく感じはSIGHTS HOTELっぽいなと思って。
確かに、参加型で巻き込みながら完成させていくところはSIGHTS HOTELに近い部分がありますね。
徹生さん:彼らは「いきいきと大人が過ごせていない今の社会は良くないのではないか」という問いをもっていました。もっと大人がみんなキラキラしていたら、子供たちは早く大人になっていろんなことをしたいと思えるし、さまざまな夢を抱くのではないか、と。
奈月さん:遊具をとおした知育や教育のボーネルンド、観光という切り口で進むSIGHTS HOTEL、手段は違うけど目指している世界は一緒だとわかって本当に良い時間でした。
その後、ビールを飲みに「キャノピー」のバーへ。そこのテーブルはスマートボール台になっていて、子供たちも喜んで遊んでいました。キッズメニューがなかったのですが、スタッフの方が「お子さんは何のジュースにされますか?」と聞いてくれて。
帰り際に伝票をみたらビール2杯分だけになってて、スタッフの方に「子供のコーラが入ってないです」と聞いたら「お子様の分はサービスで」と言われたんです。うちの子はスマートボールで遊びまくって、ポップコーンももらったのに良いの!?と思って。その時にはすでにオーダーを取ってくれた方はいなくて、お礼の挨拶ができなかったんですけど、気をきかせてくれたんだなと思って。
東京から京都へ移住してみて、関西はフランクで壁がないなと感じることが多いです。今回のテーマ「人間らしさ」にもつながっている気がします。
徹生さん:関西には、知らんおばちゃんが「飴ちゃんいるか?」と話しかけてくるみたいに喜んでもらいたいという精神や風土があると思いますね。
奈月さん:私も徹生も大阪出身ではないですが、2人ともお笑いが好きやから楽しんでもらおうという精神は常にもっています。もちろん、それが良い方向に転ぶこともあれば、苦手と思われることもあるやろうなとは思いますけど(笑)。
大阪、兵庫、京都で人との距離感やコミュニケーションで違いはありますか?
奈月さん:私は神戸の下町出身で、「おばちゃーん!水もらうで!」といって自分でドリンクを取りに行く感じで、どちらかといえば大阪に近い環境で育ちました。
徹生さん:京阪神って根っこの部分は違うんですよね。大阪は商人の街、神戸は港町。京都は朝廷があった場所。元来、京都は外から人が多く来訪する場所で、誰がいつ寝返るか分からないから、毎回人を見極めないといけなかったんですよね。いわゆる、京都の「いけず文化」はそういう時代背景から形成されたものなんですよね。
これは僕の個人的な見解ですが、ここ数十年でマスメディアが発展したことで少しノリが似てきた部分もあると思ってて。僕ら世代の関西人は「吉本新喜劇」「ちちんぷいぷい」「せやねん!」などを見て育ってきたと思うんですよね。それによって大阪のノリが入ってきたんですよね。今の若い子はYouTube世代だから全く違うと思います。「大阪人っぽい」とよく言われますが、多分それは子供ん時からそういう番組をたくさん見てきたからです。
関西文化の根底にある「人間臭さ」の魅力

その関西特有のコミュニケーションが「人間らしさ」のヒントになっているなと感じたのですが、もう少し言語化するとどんな感じになりますか?
徹生さん:実は前回、人間らしさについてはあんま深掘りできていないんです。
奈月さん:答えが出なかったんですよ。ただ、吉本の元会長の大﨑さんが書いた本『居場所。』に出てくる「人間臭さ」という言葉が良いなと思って。「人間らしさ」より「人間臭さ」の方が関西人らしいワードやなと思ったんですよね。
徹生さん:その本には「自分は優秀じゃないから、頼まれたことに一生懸命答えようと思って走り回ってきた」みたいなことが書かれていて。向上心には自己実現や自己成長のイメージがありますが、人間臭さには「この人のために汗をかこう」と他人にベクトルが向いている感じがして。そんなんが大事なんやろなと思います。
民宿やボーネルンドの話を受けて、クレイジーキルトのメンバーからはどんな意見や感想が挙がりましたか?
徹生さん:これらの話をしたときに、金融教育家が「SIGHTS HOTELはホスピタリティではなくて、どちらかといえばソサエティだと思っている」と言ったんですよ。要はホテルではなく、社会を作ることではないかということです。
ただ、メンバーで「ソサエティとコミュニティの違いは何なのか」という話になったんですよ。コミュニティは同じ趣味をもった人や同じ職業の人が集まるなど参加できる範囲が狭いのが特徴です。
その一方、ソサエティは広くて、かつその集まりに仕組みやルールがある点で違うのではないかとなったんですね。それは、スポーツのような明確なルールではなくプリンシプル(規範)があるのが特徴なのではないかなと。
奈月さん:SIGHTS KYOTOには「受け身な姿勢ではなく、主体的に挑むこと」や「境界線を無くし、多様性を重んじること」といったカルチャーがあって、これがまさにプリンシプルに近いのかなと。
プリンシプルは「しきたり」や「伝統」に近いですか?
徹生さん:倫理観が近いかもしれません。特に京都では「暗黙のルール」が大事にされていますよね。例えば、「2軒隣の玄関まで掃きましょう」がルールになっていたらそれは義務ですけど、よそさんにも気を遣うことがプリンシプルとして成立していたら素敵じゃないですか。
「ソサエティ」と「ソーシャル」は何が違うのか?
ソサエティはソーシャルと似た意味をもつ言葉ですが、どう違うんですか?
奈月さん:元々は同義の言葉なんですよ。ただ、現在日本で使われているソーシャルには「社会貢献」の意味合いが強く出過ぎていて、その人のエゴが見えない。それが面白くないし、違和感を覚えるんですよ。SIGHTS HOTELが目指しているのは多分みんなが思うソーシャルではない。
だからこそ、ソサエティという言葉は最高のヒントでしたね。ずっと私が「ソーシャルやコミュニティが嫌だ」と言っていたのが、まさにソサエティの言葉1つでスッキリとまとまったんです。みんなも「おおー!」という反応でしたし。
英語が堪能なスタッフにもこの話をしたら「ソサエティは、常に違う人が入ったり出たりして行き交っているイメージです」と言ってて、SIGHTS KYOTOに近いなと思いましたね。
公園や交差点みたいな公共空間にも近いですね。
徹生さん:そうですね。老舗企業のメンバーが「もてなす側ともてなされる側ではなく、AtoA(アクターtoアクター)なのではないか」と言ってくれました。AtoAは、BtoCやBtoBと違って取引先も商品を一緒に作る仲間なんです。
奈月さん:SIGHTS CULTUREの1つに「受け身な姿勢ではなく、主体的に挑むこと」があります。私たちは「お金を払っているんだから、もてなされて当たり前」といったスタンスがあまり好きではなくて。実際にSIGHTS KYOTOに来るお客さんも、海外旅行者の方に 「トイレはそこですよ」と教えたり、私たちに「あの人、メニューを注文したいんじゃない?」と教えてくれたりする人が多いです。
それは、この2年半で少しずつプリンシプルが形成されて、みんながSIGHTS KYOTOの存在意義を理解してくれたからですね。きっとSIGHTS HOTELもそうで、多様な人が行き交うけどAtoAで関わり合う状態が理想的だなと思いましたね。ただ、究極ソサエティを突き詰めると、ホテルである必要はあるのか?という話になってきますけど(笑)。
クレイジーキルトがRIKYUに滞在して感じたことや、どんな感想があったか教えてください。
奈月さん:いくつか出ましたね。1つが「RIKYUで何をやっているか見れて良かった」という声です。ただ、RIKYUの居心地が良すぎて少しリラックスしてしまったかな。だから皆さんいつもよりもエンジンがかかるのが遅かったかもしれないですね(笑)。
徹生さん:もう1つがRIKYUとSIGHTS KYOTOでもらっている口コミを皆で見ながら議論したときに、金融教育家が言った「ベリーローカルな場所でベストメモリーは得られる」という言葉ですね。そもそも、僕は「記憶に残ることをしたい」「心のあったまるような笑顔を作りたい」から観光業・旅行業を選んでいて。改めてRIKYUもそこを目指したいと思いました。
奈月さん:また、指揮官から出た「マッドエクスペリエンス(狂った体験)」というキーワードもヒントになりそうですね。これは、SIGHTS CULTUREの1つ「振れ幅を大切にすること」に通ずる部分でもあるので、この言葉をどう落とし込んでいくか考えてみたいと思います。
徹生さん:あとは「ラグジュアリーはターゲットを引きつける呼び水的な役割で良いのではないか」という意見も出ましたね。
わかりやすく伝えるために、あえて「ラグジュアリー」という言葉を使うということですか?
徹生さん:そうですね。一般的にラグジュアリーとして想像されるものは、全ての部屋が離れになっていて、誰にも会わずに部屋でご飯が食べられて、かつ露天風呂もついている旅館。ただ、それはクラシックラグジュアリーなんですよね。僕らが考えるラグジュアリーは料理もお風呂も良いけど、そこに泊まった人と交流できることを指しています。誰とも会わへんことを僕らはラグジュアリーと全く思わないんですよ。
奈月さん:別に言葉はラグジュアリーでなくても良いんです。ただ、なかなか旧来のラグジュアリーのイメージをひっくり返すのは難しいですね。SIGHTS HOTELの空間にきてはじめて「ニシザワステイはこれをラグジュアリーと呼んでいるのか」と思ってもらえればそれで良いのかなと考えていますね。
京都は、日本の美意識や起源が凝縮された場所。そこにこそ社会の「本質」が眠る

お二人は「本質」について、現状どのように考えていますか?
奈月さん:正直なところ、まだ明確な答えが出ていないのが現状です。クレイジーキルトのメンバーからは、本質や人間らしさの言葉そのものが広すぎるのではないかという意見をもらいました。
徹生さん:「○○な人間らしさ」や「○○な本質」みたいに、主語を小さくした方がわかりやすいという話は出ましたね。
話を聞く前は、「お2人が考える本質」だと思ったんですけど、ここでいう本質は社会に紐づいてるものなのでしょうか?
徹生さん:そうです、社会の本質です。私たちはお寺さんと仕事する機会が多く、仏法の教えについて聞くことがあります。そのたびに、約2,500年前に生まれたお釈迦さんの言葉は今なお我々を突き動かすパワーがあり、今でも脈々と受け継がれていると実感するんですよね。そういう起源を辿ることも、また本質ではないかなと思っていますね。英語だとオーセンティックやオリジンに近いのかな。
奈月さん:新しくSIGHTS HOTELを作るけど、本質は人と人がリアルでコミュニケーションを取り、京都を知れる場所。だから、本質は不変でずっと存り続けるものです。
以前の取材で「京都でやることに意味がある」といったお話をされていました。それは京都の本質を伝えたいからですか?
徹生さん:そうですね。京都ひいては日本の本質を伝えていきたいです。京都は、日本の価値観や日本人の美意識など日本の起源が凝縮された場所だと思っているからです。
奈月さん:私たちが手掛ける対話型プライベートツアー「1 / KYOTO」の対談者の方々は「京都は新しい文化が入ってきても、原点に戻れるところがある街だ」と言います。私たちも京都に住んでいるからこそ、そういう思考で事業ができるんだと思うし、それは子供たちにも大事なことやと思ってて。今東山に住んでいますが、近くには建仁寺や清水寺があって、いろんな商売をしているおっちゃんがおって、そういう人たちから非常に多くのことを学べると思っています。
京都の本質というのは、コミュニケーションの部分か、それとも歴史が深いことなのか、具体的には何を指していますか?
徹生さん:まず1つは自然との共生です。京都に節句が残っているのも、ある意味自然との共生だと思うんですよね。自然に抗わずに、むしろそれを楽しむ。
もう1つは敬いや畏れですね。天災など抗えないものに畏怖する心、自分の上にある目に見えないものにリスペクトをもつ心。それは身近に神社仏閣がある京都だからこそ根付いている考えなのかなと。
もし、SIGHTS HOTELをとおして世界中に日本や京都が大事にしている価値観を広めることができたら、その意思を継いだホテルがたくさんできるかもしれないと思っていますね。