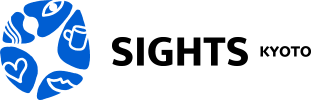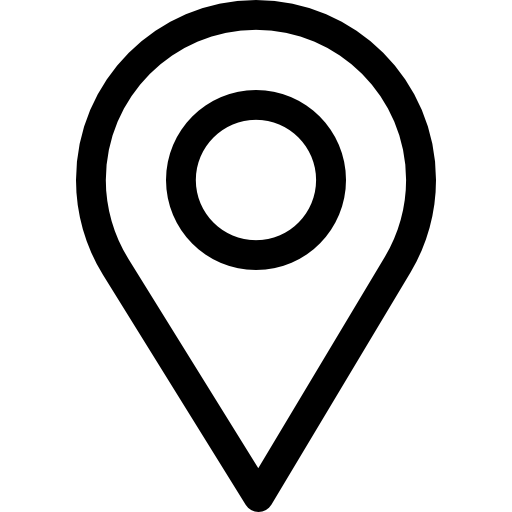SIGHTS KYOTO代表の西澤徹生と、西澤が話を聞きたい方とのビジネス対談企画!
このSIGHTSNESSではSIGHTS KYOTOコワーキングスペースの契約企業のメンバーはじめ、弊社ニシザワステイの取引先やSIGHTSに関わる方々と、普段は照れくさくてなかなか聞けないビジネスのお話やビジョンを語り合いたいと思っています。
さて、そんな本企画の記念すべき第一弾は…
昨年夏からSIGHTS KYOTOを京都の拠点として活動されている株式会社ゼロワンブースターキャピタル・立山冬樹氏との対談をお届けします!
===
▼ゼロワンブースターキャピタル
ゼロワンブースターが10年かけて培ってきた事業創造エコシステムを最⼤限に活⽤し、スタートアップに最適な成⻑戦略をサポートし、将来の成⻑に期するイグジットの実現を⽬指すファンド。
https://01booster.co.jp/program/01capital
▼ゼロワンブースター
「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開する事業創造パートナー。
https://01booster.co.jp/
===
Contents
ゼロからもっとプラスにしていくことで、地域の経済を盛り上げたい
徹生「じゃあ、まずは立山さんの経歴から伺っていきましょうか!ゼロワンブースターキャピタルには2年前に入社されたということですが、それまでの経歴はどんな感じだったんでしょうか?」
立山さん「まず新卒で地元の銀行に入りました。『地域の経済をもっと盛り上げていきたい』と考えたときに、それができるのってやっぱり銀行かなと。そこで最初は企業再生を担当していて、経営が危なくなって返済をストップしている企業がどうやったら返済再開できるようになるか、経営が回せるようになるか・・とかをやっていました。あとは船や飛行機、発電所向けの融資。いわゆるプロジェクトファイナンスにも携わっていましたね。」
徹生「なるほど。当時はスタートアップとかまったく関係ない領域だったんですね。」
立山さん「そうなんです。ただ、特に企業再生って『マイナスをゼロに戻す』という形じゃないですか。それはそれで意義は大きいものの、それよりもやっぱり『ゼロからもっとプラスにしていく』ことをやっていきたいなというのは当時からずっと思っていたんです。まぁでもそれもいずれ銀行でできることだし…と、そんなことを考えていたときにたまたまその銀行のVC(ベンチャーキャピタル)に転勤することになりまして。それまでの仕事も好きでしたけど、まさに『ゼロからもっとプラスにしていく』ということができるVCという業界、そしてスタートアップという領域にすごく関心を持つ入口となった転機でした。」
徹生「そういう経緯でこの業界でのキャリアがスタートしたんですね。VCへ行ってからはいかがでしたか?」
立山さん「やりながら感じた課題もありました。当時は、結局『上場を目指さないと投資対象にはならない』というような意見も非常に多かったんですよね。もちろんお金の仕事をしている以上はIPOの方がリターンが出しやすいとは理解しつつも、地方の経済を起点にした時、IPOだけを選択肢にすることで、もっと大きな産業が生み出される機会が損なわれている感覚もありました。スタートアップにもIPOだけでなくM&Aという選択肢があるはずなのに、その仕組みが当時はまだ世の中に浸透していなかった。そこをちゃんと自分が実践できないといけないと感じてM&Aの会社に転職し約2年半、そこでスタートアップのM&Aの仕事をさせていただきました。」
徹生「その次の会社がゼロワンでしたっけ?なにかきっかけがあったんですか?」
立山さん「そうです。M&Aの仕事は非常におもしろく、やりがいもあったんですけど、VCとM&A両方経験した上で改めて『どちらをやっていく方が自分の目標に近づけるのかな』って考えたときに、やっぱり投資のときから関わって長い目線で伴走していけるVCの方に戻りたいなと思ったんですね。会社には早々に辞める宣言をしたものの、次の仕事は決めていなくて。前々から浜宮さん(ゼロワンブースターキャピタル・取締役パートナー)とは知り合いでよく飲んでいたので、『実は会社辞めるんですよ』『じゃあうち来ませんか?』という話をきっかけにゼロワンに行くことになった…という流れです。」
ゼロワンのアンチテーゼ文化!”頭揺らし会”で既存の常識を取っ払う
徹生「では、ここからはそのゼロワンについて深堀りしていきたいと思います!立山さんはゼロワンブースターキャピタルのどういった部分に共感して入社されたんですか?」
立山さん「元々2012年にゼロワンブースターという会社ができたのですが、僕が所属しているのは2022年にファンドという形で立ち上がったゼロワンブースターキャピタルという会社です。ゼロワンは、事業創造をビジョンとして掲げていて、元々『事業会社の持っているアセットを世の中に開放してどうやって事業創造していくか』というノウハウやネットワークを持っているため、ファンドの中でもLP投資家の方からお金を集めて投資しますということだけではなくて、その先の成長機会の創出などにも強みがあります。スタートアップが事業を成長させていくためには当然自力でやっていかなければいけない部分もありつつも、そういうノウハウやネットワークをすでに持っている既存の事業者たちと一緒になって成長していくことで戦略をより高められると思うんです。」
徹生「なるほど!少しM&Aに近い要素もあるような気がしますね。」
立山さん「そうなんですよ!M&Aだと完全にグループが一緒になるという大きい行為ですが、もうちょっと緩やかに業務提携みたいな形でやっていくのも広い意味でM&Aの企業統合行為の一つなので。そういったところも含め、自分のやってきたM&Aの思想ともすごく近いなと感じたのでゼロワンに来ました。」
徹生「おぉ~、そうつながっていくんですね。他のVCとは違う、”ゼロワンならではの強み・特徴”って他にどんなところだと思います?」
立山さん「なんか思想的な…ちょっと面倒な話になっちゃうんですけど。(笑)」
徹生「いいっすね!」
立山さん「たとえば僕たちは『スタートアップとはこうあるべきだ』『これがセオリーだ』みたいなHOW TOを本当に嫌うんですよ。当然、それが合っていれば正しいんですけど、そもそものWHYの部分が抜けてしまっているケースがすごく多くて、テクニックとして正しいように見えても、本質的な部分で合意ができないと納得ができないメンバーが多いです。」
徹生「既存のセオリーや常識的なものは取っ払う?」
立山さん「そうです。そういうHOW TO話に寄っていくと、必ず誰かがアンチテーゼを投げかけに行きます。(笑) 事業会社の新規事業開発では、他社の成功事例をそのまま自社に取り入れようとするケースも多いです。ただ、その場合でも他社の事例や制度で公表可能とされているものを参考として共有することはあっても、まずそのままはやらない。他社に最適化されたものが自社にそのまま当てはまるかはわからないですしね。まず真っ先にやるのは“頭揺らし会”です。」
徹生「なんやそれ!ヘッドマッサージみたいな?」
立山さん「いや、もっと激しいですね。(笑) 『あなた方は何がやりたいのか?』『なぜできないのか?』を問うて、頭をグワァ~っと揺らして今までの考えを一度取っ払う。たとえば大企業さんって何千億、何兆円っていう売上で安定させて経営を回している時点でそれはすごいことですし、中にいる人たちももちろん優秀です。ただ、それまでのその会社でのやり方において最適化された優秀さであって、だれもやったことのない新規事業開発の領域においてはこれまでにやったことのない新しい経験や力が必要になることが多いです。」
徹生「新規事業開発は既存の型や価値観に当てはめて生み出せるものではないですね。既存のものにアンチテーゼを投げかけて、『何がしたいか、なぜしたいか』という深い問いを投げかける…。まさに自分たちも常に大事にしていることなので、その思想はめちゃくちゃ共感できます。」
今年1月からついに京都で始動!事業会社の中に眠る才能を発掘する『SPIN X』
徹生「まさに先ほど新規事業開発のお話が出ましたが、立山さんの所属するゼロワンブースターキャピタルは現在、事業会社に眠る才能を”スピンオフ・スピンアウト”により発掘するプログラム『SPIN X』を運営されています。これについて少しご説明いただけますか?」
立山さん「『SPIN X』とは、事業会社の中に眠っている技術や知見を会社の外へ出し(=スピンオフ・スピンアウト)、より成長できる環境下で事業を行い、外部のリソースを活用しながら急速に成長することを支援するプログラムです。事業会社の中で生まれた高い技術や他社に真似できない知見が生まれたとしても、技術そのものが悪いのではなく、例えば既存事業とはシナジーがないなどの理由で、社内で使われずに眠っていることが多くあります。いい種があることで、その種が花を咲かせるためにより適した土に植え替えると言う考えに近いです。プログラムの中では、特にスタートアップファイナンスに関して重点的に話をしています。これもHOW TOの話ではなくて、スタートアップファイナンスってそもそもどういう思想なのかを体験してもらうためにグループワークで1つゲームを回してもらいます。事業会社の中にいる人たちって社内で予算をとることはあっても、たとえば銀行や投資家といった外部の人との会話ってほとんどしたことがない。そもそもお金の出し手がどういう思想なのか、どういうロジックで回っていてどこに納得感があるのかを徹底的に体感してもらうというのが大きなベースになります。」
徹生「なるほど!分かりやすいです。これまで東京で4期にわたり、約90社の事業会社が『SPIN X』に参加されたという実績があるんですよね。東京では大企業の参加が多かったのでしょうか?」
立山さん「そうですね。割合としては大企業が多いですが、プログラムでは会社の大小を前提とはしていません。スピンオフを考える際には”技術”と”人”の2軸で見る必要があって。まず技術面でいうと、大企業が技術を持っている割合は高いですがそれが市場に適合して伸びるかどうかはまた別の論点。逆に会社規模は大きくなくとも、何代にもわたり受け継がれている技術が伸びることもあります。そういった意味で、市場に出ることで大きく事業として伸びる可能性がある技術がどこにあるかという点で会社の大小はそこまで大きな違いはないと考えています。一方で、人の面に関しては違いがあります。大企業はいくら人手不足と言っていても、誰かが起業家として外に出たなら代わりの人が人事異動でやってくるので会社の屋台骨は崩れにくいですよね。それに対して、中堅企業ではエース級の人材が出ていくとなると会社は代わりになる人材が相対的に不足しているケースもあり、本業側としては困るという傾向があります。なので、この点については代替策をどうするかをしっかり考えていかないといけないです。ただ、こういったスピンオフによる事業開発の取り組みはそもそもHOW TOをパッケージとしてやっても意味はなく、それぞれの会社によって発生する論点を丁寧に合意していかないといけないです。こういった違いがあるということを念頭に置いて考えるというだけであって、本質的に事業会社の規模による違いはないと考えています。」
アップデートするからこそ残る、京都は”技術の街”
徹生「そしていよいよ、ここから京都の話になっていきます。『SPIN X』の第5期がなんと、今年1月に京都で始まりました!次の舞台に、京都を選んだ理由は何なのでしょう?」
立山さん「日本の中にはいい意味でまだまだ眠っているものがあって、どれだけすごい技術でもその会社の中にあることで成長に制約がかかってしまうことがあります。例えば、これまで既存事業でto B向けしかやったことがなくてto C向けが分からなかったり…という話がたくさんあります。それを外に出し事業展開していくことで、やり方を変えることで、本質的な価値が広がる場があるということをこれまでの経験で気づかせてもらいました。そんな中、こういった技術って日本国内のどこにあるんだろうと考えたときにまず思い浮かんだのが京都だったんです。京都って観光のイメージが強いと思うんですが、実は伝統産業技術や先端技術も含めて“技術の街”だと受け止めています。技術を今の形のまま残すだけではなくて、その技術をベースに新しいことをやって事業として成り立てば自動的にその技術が残る。そういった残し方と広げ方の両方の意味合いで考えても、やっぱり京都は強いなと。」
徹生「今の話すごく納得です。僕は生まれも育ちも京都なんですが、1000年つづいた都であり“不易流行”や”伝統と革新”という言葉もあるように、時代に合わせてアップデートしたり変化させたりしてきたからこそ残っているものが多いのだと感じています。きっとそのまま残すだけではここまで続いていない。形よりも大事なのはその心や本質で、そこを残しながらアップデートされたものが人のためになり、役に立つということは非常に大事なことですよね。まさに京都が京都であり続ける理由だと思います。中にいると視野が狭くなってしまうところを、こうやってゼロワンさんみたいに外からの目で見てくれて発掘してくれる存在がすごく重要ですよね。実際に『SPIN X』を京都でスタートさせてみて、どんな感触がありますか?」
立山さん「すごくいい方々に集まっていただいていますし、やっぱり素晴らしい技術を持った会社さんが多いなという印象ですね。思っていた以上に技術の種が多いです。前章でお話したように、スピンオフ・スピンアウトというのはあくまで手段。それが適合するかどうかは会社や状況により変わってくるので押し売りする気はまったくないのですが、京都は土壌があるからこそ選択肢の一つとしてこういうものもありますよ、ということを今お伝えしているところですね。これが正しかったかどうかは、本当に5年後、10年後どうなっているか、これからの活動にかかっていますので、信じて歩くしかないと思います。」
徹生「これからの数年で、『SPIN X』の他にもいろんな手段が出てきそうですね。いや~楽しみです。」
非ロジックな世界 SIGHTS KYOTOで生まれた偶発性と直感
徹生「最後にこれを聞かないと、うちとしては終われません。(笑) ズバリ!なぜ京都の拠点をSIGHTS KYOTOに決めてくれたのでしょう?」
立山さん「一言で言っちゃうと『直感で周波数が合ったから!』ですね。(笑) ゼロワンブースターも東京でSAAIという施設を運営しているんですが、コワーキングスペースではなくコミュニティスペースと表現していて、ハード面よりもソフト面、コミュニティを大事にしています。単に仕事する場所としてであれば家やカフェ、出張中のホテルでもいいですが、なんかそれではもったいないという感覚があって。事業でも結果上手くいって振り返ったときに『あのときあの人と会ったから。』『あの人がいたからよかったんだよ。』というのが絶対あると思うんですよ。偶発性や偶然の出会いみたいな非ロジックな世界を僕たちは信じていて、そういう機会がある場所がいいなと思っていたらまさにSIGHTS KYOTOが。(笑)」
徹生「その出会いが去年7月に京都で開催されたIVS KYOTO 2024のサイドイベントでしたね。会って話したその流れですぐ『入ります。』はびっくりしましたけど(笑)、観光業を生業としている者として僕たちも偶発性やご縁みたいなものはすごく大事にしているので、これは一番嬉しいですね。」
立山さん「あのとき拠点探しでいろんなコワーキングスペースを見させてもらったんですけど、実際ここに来てみたら場所も綺麗だし、1階はバーで賑やかだし。僕たちお酒飲むのも好きなので、真面目な話もしつつ軽く一杯どうですかって形で交流のできる場所は魅力的でした。あとやっぱり徹生さんと奈月さんの人柄含め、あの盛り上げ方。(笑) あれがすごくいいなと思って、浜宮さんと1階のカウンターで飲みながら、お互い真っ赤な顔して『ここじゃないですか?』『うん、ここだね。』って話をしたのを今でも覚えています。(笑)」
徹生「やっぱりVCとして、人を見る目・直感は大事にしていらっしゃる?」
立山さん「かなり大事にしていますね。逆に外形上はいいんだけどなんか直感的にモヤっと引っかかるなということも無視できないですし。SIGHTSをいいなと思ったときは特に理由を話さなくても浜宮さんも同じこと思っているなと分かりましたし、僕たちが大事にしていることとSIGHTSの波長が合っているというのは真っ先に感じましたね。言葉ではうまく言えないですけど。」
徹生「言葉にできない感覚って僕たちもすごく大事にしています。あの日お二人と話した瞬間に『この人たちはおもしろいから仲間になりたい!』と速攻でゴール決めにいきましたね。”東京のVC”ってなんか胡散臭そうな…と少し構えていたんですけど、お二人ともめちゃくちゃいい方で勝手に抱いていた東京のVCへのイメージが払拭されました。(笑)」
立山さん「分かります、分かります。東京からVCが来るって、『怪しそう。どんなヤツらなんだ。』って普通そう思いますよね。(笑)」
徹生「では最後に、今後『SPIN X』に参加されるかもしれない京都の企業の方々にメッセージをお願いします!」
立山さん「技術を持っている企業さんって、自分たちが技術のすごさに一番気づいていないっていうことがめちゃくちゃあるんですよ。ずっとその社内にいたら『こんなもん誰でもできるでしょ。』って言うんですけど、外から見たら『いやいや、それ誰もできないですよ。何言ってるんですか!』って。(笑) それって技術の価値を認めていないのではなくて、ずっと中で見ているからこそその価値が外から見たときにどれだけすごいものなのかって気づいていない。そこがすごくもったいないなと感じる瞬間があるので、どんな技術があって、それを使ったらこういう選択肢があるかもっていうところを是非一緒にお話したいなと思っています。」
徹生「それは…やっぱり飲みながら?(笑)」
立山さん「ですね。そういう話はまずは飲みながら、がやっぱりいいですよね。(笑)」
徹生「いや~、ゼロワンさんはコミュニケーションを大事にされているところが非常に素敵ですね。引き続き、どうぞよろしくお願いします!」