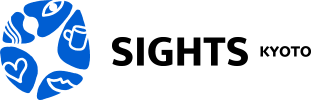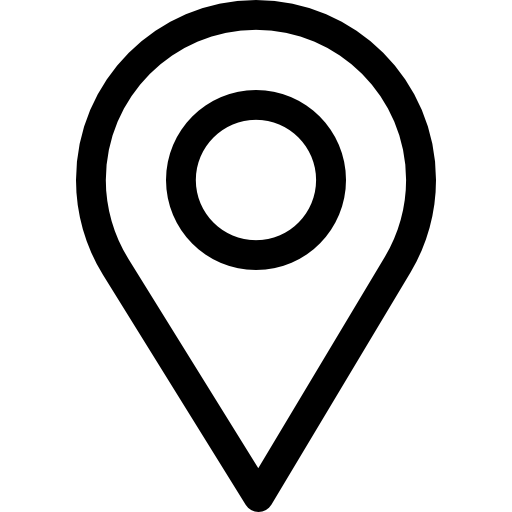2030年に開業を目指す「SIGHTS HOTEL」。実は水面下で、秘密裏にプロジェクトは進められているとか、いないとか……?この連載では、「SIGHTS HOTEL」が完成するまでに至った苦悩や試行錯誤の様子や姿を、ありのままに映していきます。ぜひ、読者の方も一緒に「SIGHTS HOTEL」を考え、妄想してもらうきっかけ作りになれば良いなと思っています!
具体的には、主に「SIGHTS HOTEL」についてゼロから考える「クレイジーキルト」で議論された内容を踏まえ、西澤夫妻が得た気づきや学びをまとめていきます。連載企画のインタビュアーを務めるのは俵谷龍佑(たわらや・りゅうすけ)です。西澤夫妻とは1988年生まれ、同世代!
・・・
Vol.4のインタビューを実施した4月はSIGHTS KYOTOの3周年。SIGHTS KYOTOのリブランディングを行うなど大きな変化がありました。「SIGHTS HOTEL」の計画はどのような進展を見せたのか?今回も、「ラディカルサークル」や「意味のイノベーション」など、興味深いキーワードがたくさん!?
Contents
コンセプト「LOBBY LOUNGE OF KYOTO」に込めた想い
まず、SIGHTS KYOTOのリブランディングを実施した経緯について教えてください。
徹生さん:KYOMACHIYA-SUITE RIKYUや「1 / KYOTO」ではラグジュアリーを実践しているのに、我々が考えるラグジュアリーをSIGHTS KYOTOで提供できているのかと思ったのがきっかけです。
奈月さん:SIGHTS KYOTOには若くて明るいスタッフが多いがために、親しみやすさやポップさが前面に出てしまっていると感じました。これらの要素は大切にしつつも、もっとメリハリをつけていきたいと思っていて。なので、リブランディングを機に公式Instagramもリニューアルしました。遊び感のある投稿を減らし、原色でポップな色合いから洗練された雰囲気に変えました。
徹生さん:我々が考えるラグジュアリーを正確に認識してもらえるように、広報のマリーと議論し合って完成したのが「LOBBY LOUNGE OF KYOTO」というコンセプトです。SIGHTS HOTELとの親和性はもちろん、品格や多くの人が行き交っているイメージ、京都の奥につながる雰囲気など、我々が伝えたいものが全て内包されている言葉だと思ったんですね。
東京視察では、何を見に行かれたのでしょうか?
徹生さん:コンセプトが決まったので、改めて帝国ホテルや丸ノ内ホテル、ザ・ペニンシュラ東京、パレスホテル東京といったラグジュアリーホテルのロビーラウンジに行きました。
奈月さん:昔、1度だけ帝国ホテルのロビーラウンジに行ったことがあって。打ち合わせをしている人や宿泊客、お相撲さんなど多種多様な方がいておもろいなと思ったんですよ。コンセプトが決まる前から、徹生と私の中では「帝国ホテルのロビー」というワードが何回も出てきてて。
特に、今回の視察で印象的だったのが渋沢栄一氏の言葉でした。帝国ホテルの歴史を展示しているエリアには、初代会長である渋沢栄一氏の言葉が書かれていたんですね。

徹生さん:わかりやすく噛み砕くと「いろいろな国からのお客さんを迎えるのはとても大変だけど、世界の隅々に日本の懐かしい思い出を持って帰ってもらうことができる、外交官のような仕事である」といったことが書かれています。これは、まさに「日本の迎賓館」の役割をもって誕生した帝国ホテルの歴史とも重なるメッセージに思えました。
そこから、「迎賓館」について二人で考えていました。「迎」はウェルカムで、「賓」は大事なお客さん、「館」はハウス。「そうか、大事なお客さんを迎える館なのか……!」とピンときたんです。
奈月さん:大事なお客さんを出迎える場所であり、そこには互いに尊敬し合う気持ちがあるからチープではダメだし綺麗にしとかなあかんのかと思って。ラグジュアリーでなければならない理由ともつながりました。
クレイジーキルトでは、どのような反応やフィードバックが返ってきましたか?
徹生さん:前回を含めここ数回のクレイジーキルトは全員参加ではなかったため、今回は、これまで話してきたことを振り返りつつ、東京視察で得た気づきや学びと、僕がお坊さんから聞いた「観音菩薩」のエピソードについて話しました。
「観音菩薩」に含まれる“観”の漢字には「心の目でみる」という意味が込められているそうです。一般的には「見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触る」といった人間に備わっている感覚を五感といいますが、仏教の世界では「心」を加えて六根といいます。本来、観音様は声にならない声や悩みを心の目でみてくださる存在なんです。観光も同じように、何かを目で見たり口でわったりするだけでなく、心で営みや歴史を感じとることが大事だと思っていて。
奈月さん:「迎賓館」や「観光」のエピソードのあとに、前回盛り上がった「ダイナマイトバディ戦略」の深堀りの方向に話をもっていきたかったのですが、あまり皆に刺さらず……。「ダイナマイトバディ戦略」とは、上のボンの部分でオープンに様々な人を受け入れながら、キュッの部分で互いに精査し、絞られた人が下のボンであるソサエティに入っていく…という構図です。

徹生さん:この戦略を実践するためのキーが我々であり、SIGHTSスタッフです。オープンに受け入れた多様な人をしっかりと見極め、あの手この手を差し出してそれぞれに合った選択肢や関係性につないでいく……。「その姿はまさに千手観音じゃないか!」と、自分たちの中でピンときたことを「ダイナマイトバディ観音さん」で表現したのですが、まったく伝わりませんでした(笑)。
なぜなのか聞いてみたら、クレイジーキルトの半数から「そんな抽象の話をずっと続けていても何も進まないし、そろそろ具体の話をしたい」と言われて。僕らからすると、まだ深掘りしきれていない感覚があったんですね。
奈月さん:仮に「WELCOME TO OUR SOCIETY」がコンセプトだとして、それを頼りに具体の話を進めるのはまだ難しいと感じたんです。気が付いたら西澤2人vsクレイジーキルトの構図になって、第1回目と同じくピリついた空気になってしまって。仕切り直すべく、クレイジーキルトを1回ストップさせてラディカルサークルを挟むことにしました。
意味を問い直す対話──ラディカルサークルでみえたSIGHTS KYOTOの原点

そもそも、ラディカルサークルとは何ですか?具体的にどんなことを行う会議体か教えてください。
徹生さん:著書「突破するデザイン」に登場する「意味のイノベーション」という思考法のプロセスの一つです。まずは、個人の内から生まれた弱くて脆いビジョンを、ペアによるスパーリングでより深く強固なものにします。その次が複数のペアから成るラディカルサークルで、その主目的は「同じ方向を見ている精神的励み」と「建設的な批判」を受けることです。“批判”とは、「より深くモノゴトを解釈していく取り組み」であって否定ではないんですね。
奈月さん:結局、私たちはクレイジーキルトのメンバーから否定してほしいわけでもなく、アイデアがほしいわけでもなく、一緒に意味を見つけて深めていきたかったんです。この会は西澤の発表会でもないしバトルでもない。同じ方向を見たうえで、それぞれが持ち寄った意味を衝突・融合させる必要がありました。
今回、どのようにしてラディカルサークルの人選をしましたか?
徹生さん:クレイジーキルトのメンバーを具体と抽象でカテゴライズして、より抽象に強いメンバーである指揮官と金融教育家、次に抽象に近い2人、我々を加えた計6人で、第1回目のラディカルサークルを行いました。
奈月さん:指揮官と金融教育家の2人とはクレイジーキルトのあとに2次会へ行くことが多く、結果的に私たちと対話を重ねた数が多かったんです。「SIGHTS HOTELはホスピタリティ論ではなくて、どちらかといえばソサエティ論だと思っている」というキーワードとなる言葉も金融教育家が出したものだし、指揮官は私たちの方向を導いてくれていました。つまり、この4人で自然とラディカルサークルができていたんですね。
ラディカルサークルでは、どのような議論が交わされましたか?
徹生さん:金融教育家が、「ホテルから考えるとしっくりこないんだよな……もっと大きな概念を作ろうとしている気がする」と言い出して。
それで、SIGHTS KYOTOの話をしたんですよ。確かにSIGHTS KYOTOも上位概念を実現させる手段として、結果的にコワーキングスペースとBARになったんです。この辺りは、先ほど言及した「意味のイノベーション」にも非常にリンクしているところで。意味のイノベーションとは、自身の内面から湧き上がる情熱やアンチテーゼを起点に思考するフレームワークです。これの対になる言葉が機能的な改善や市場のニーズなど外の声を元にサービスや商品を構築する「問題解決のイノベーション」になります。
奈月さん:SIGHTS KYOTOも、内側から湧き上がる情熱やアンチテーゼから作ったなと思って。コーヒーマシンがあったら便利だけど、ユーザーに要望を聞いて作っていたら他と変わり映えのしない空間になっていたと思うんです。
徹生さん:僕らは「コーヒーが欲しかったら1Fに買いに来ると思うし、なんなら生ビールを推した方が面白いんじゃない?」と思って。そうしたら「確かに!これはこれでおもろいな!」と、SIGHTS KYOTOのスタンスに面白がってくれる人が増えて、今やビールを片手に打ち合わせする光景をよく見かけるようになりました。
奈月さん:そのあと「西澤が大事にしたい人は誰なのか?」と聞かれて、「ソサエティにいる人たちを幸せにしたい、豊かにしたい」という結論に帰着したんですね。
徹生さん:一見さんの海外旅行者の方も幸せにしたいけど、それ以上に普段からお世話になっているステークホルダーの人たちを幸せにしたいということに気づいたんですよ。
「まずは、身近の人を幸せに。」から始まる

オープンの人が来る場所とソサエティにいる人たちがいる場所を分けても成立するのかなと思ったのですが、あえて混在させる理由は?
徹生さん:分けると“コミュニティ”になってしまいます。それは僕らが理想とする空間ではないんですね。「WELCOME TO OUR SOCIETY」を成立させるには、オープンの人とソサエティの人が同じ空間にいることが重要です。
奈月さん:SIGHTS KYOTOには「皆とてもフレンドリーで楽しいBARだった!」と喜んでくれる方がいる裏に、実はスタッフと同じように自主的に動いてくれる常連さんの存在があります。
徹生さん:ここでポイントなのが、“ついつい、もてなしちゃう”ところだと思っていて。この前、俵谷さんご夫妻も京都に移住してこられた方を連れてきてくださったじゃないですか。まさにあれなんですよ。だから、SIGHTS KYOTOに来ている回数は関係なくて、気づいたらソサエティに入っている常連さんがいるんですよ。
奈月さん:私たちやスタッフだけでなくて、ソサエティにいる人も一緒にもてなしている状態ですね。それが100人、200人になればもっと良い空間になるし、京都はもっと良い街になるのではないかと思っています。
そして、みんなをオープンに迎え入れた結果、ソサエティにいる人たちも今日来て良かった、豊かな時間を過ごせたなと、何か気づきや学びが得られる空間にしたいんですよね。
ソサエティを大切にすることで、結果的にオープンの間口が広がっていく。良いサイクルを作ることができるわけですね。
奈月さん:会員限定のBARやコワーキングスペースをやりたいわけではないんですよ。そこに突拍子もなくブラジルの人やアメリカの人が来るからこそ、化学反応が生まれるじゃないですか。
徹生さん:ソサエティに入る基準はお金ではないんですよ。プリンシプルやカルチャーに共感しているかが重要で。「誰がソサエティに入る基準を決めるのか」という話になったときに、「やはり、西澤夫妻なんじゃない?」という結論になったんですよ。ソサエティに入る基準の一つとして、西澤がスタンプを押すという条件ができたことで、幸せにしたい人の数やソサエティの規模のイメージがつきましたね。
奈月さん:実際に会って認識し合える人をどれだけ幸せにできるかが大切だと気づきました。そうなると、自分たちが「ホテルのどこでどんな動きをしてるか」というイメージも少しずつ見えてくる気がしています。
徹生さん:どこか遠い国の人ではなくて、今自分たちを支えてくれている人たちこそがソサエティの人たちだと思っています。ソサエティにいる人たちが、外からの人をもてなすようになれば、SIGHTS KYOTOもまるで初めて会ったとは思えないアットホームな空間になると思うんですよね。
あと、話題に挙がったのが「ホテルの顔」についてです。ここ10年、20年ぐらいホームページや予約サイトのメイン写真は客室であることがほとんどですよね。ただ、SIGHTS HOTELは客室ではなくてロビーラウンジが顔やと思うんです。
つまり、ホテルの顔は「客室」ではなく「人」だ、と。
徹生さん:そうですね。SIGHTS HOTELのメイン写真はステークホルダーが行き交うロビーラウンジで、そこには顔となるロビーマネージャーがいるイメージです。JTB時代に、まさにこのロビーマネージャーのモデルとなる役割があって。我々はJTBのときに窓口業務をしていたのですが、混んでいるときに支店長が「お待たせしてすいません。案内前に少しヒアリングしますね」と並んでいるお客さん一人ひとりに声をかけてくれてはったんですよ。
奈月さん:一人ひとり丁寧にヒアリングして、その情報を私たちにつないでくれて。「ダイナマイトバディ観音」はまさにJTB時代の上司をイメージしたものなんです。
徹生さん:「SIGHTS KYOTOはコワーキングスペースにあまりお金を使っていなくて、1階にとてもお金を使いました」という話をしたんですね。そうしたら、指揮官が「なるほど!つまり客室にいたくなくなるような、ロビーラウンジに行きたくなるような、居心地が悪いホテルだ」と言い出して。
なるほど……!「人と交流する仕掛けがあるからこそ、客室の居心地が悪くなる」ということですね。
徹生さん:そうなんです。例えば、客室にはワークデスクもないしお風呂もシャワーしかない、寝るだけの最低限の機能だけ揃える。もちろん、お客さんを迎える以上は寝具やパジャマなどは非常に上質なものを選びます。
仕事がしたければコワーキングスペースで、お風呂に入りたければ大浴場といったパブリックな場所を使ってもらう。氷が欲しければロビーまで降りてきて氷をもらう。そして、降りてきたらめっちゃ喋ってもうて、なかなか部屋に帰られへん(笑)。これは、SIGHTS KYOTOもそうで2階のコワーキングスペースにドリンクバーや冷水機を設置しないのはそういう理由があるからなんですよね。
奈月さん:どうにかしてBARとコワーキングスペースをつなげたかったんです。もちろん、2Fにコーヒーマシンを置いた方がユーザーは便利ですよね。でも、それだと帰るまで絶対に1FのBARに降りてこないと思ったんです。
徹生さん:「わざわざコミュニケーション取りたくないから、2Fにコーヒーマシンを置いてくれた方がうれしい」みたいな人には居心地が悪いと思うんです。
奈月さん:だから、あえて2FにはWi-Fiのパスワードもドリンクメニューも設置していないんですね。一見無駄に思えることも、全て「どのようにしてコミュニケーションを生むか」と逆算して考え抜いた結果なのです。
徹生さん:他にも、大浴場の洗い場にはあえて2席おきにシャンプーを置いて、「ちょっと借りていいですか?」と隣の人と自然発生的にコミュニケーションが生まれる設計も面白そうだとか(笑)。
奈月さん:大喜利大会が始まって(笑)。
徹生さん:「どうすれば、ロビーラウンジで出会いの偶発性を作れるか」という議論は広がりが出るし、やはり面白いですよね。次回も楽しみです!